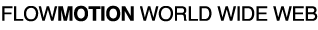2005年8月10日
「デフ文化村」が1年間の営業を終えました。
さて、「デフ」とは?
「デフ」はろう者という意味です。
「デフ文化村」は耳の聞こえない乗富秀人御夫妻の行動力で生まれた夢の場所でした。
カフェ機能のある「耳の聞こえない人」と「耳の聞こえる人」との緩やかな交流の場。お互いの文化を発信しあえる場。運営は乗富秀人さんたちの行動に感応した人たちが参加しました。
タカサカと乗富秀人さんの出会いは2003年です。FLOWMOTIONのリオープン直前の準備中のことでした。
地元の新聞に掲載された「カフェと雑貨とギャラリーがあっていろんな人たちが交流できるスペースがFLOWMOTIONです」というタカサカの言葉を読んで訪ねてきてくれたのでした。
乗富秀人さんが画家であること、将来「デフ文化」を発信できる場所を持ちたいことなど、色々なコトを筆談しました。文字一杯のレポート用紙が重なっていくのを見て、おしゃべりの分量を視覚的に感じた初めての日でした。
手話の存在に直接触れた初めての日でもありました。
まったく実用に感じられなかった表現が瞬間的に必要に感じられました。そこで、FLOWMOTIONで手話教室を開くことにしました。先生は乗富秀人さんの奥様カズコさんです。2005年現在も継続中で「日本手話」と「アメリカ手話」をしています。手話は世界共通という勝手な思い込みがありましたので驚きでした。
方言もあるといいます。「東京」と「帯広」で若干ニュアンスの違いがあるそうです。考えてみますと当たり前のこと。手話は身ぶり手ぶりです。その国、その地方の習慣が直接現れる身体表現言語です。その地その地で意味が通じないといけないものです。なのでソコココで手話が生まれていくのは当然のことだったのですね。
では、手話の簡単なイメージを、、、
日本手話の「ありがとう」はお相撲さんが勝って懸賞金をもらう時にする感じです。拝む感じになります。
アメリカ手話の「サンキュー」は「投げキッスのイメージ」です。口元に手を置いて相手に向かって投げるのです。表現の多様性に感心します。
乗富秀人御夫婦の活動は周辺をまきこみ、遂に2004年の7月に「デフ文化村」をオープンさせます。
耳の聞こえない二人がカフェと文化交流の場所を作ったということは新聞やテレビでもニュースとして取り上げられました。
オープン前にいろいろと話をする機会がありました。
タカサカはお店に音が必要かどうか考えたものでした。カフェには音楽が流れているのが当たり前に思えたからです。けれども乗富秀人さんたちには聞こえません。いろいろ思いを巡らして、音がなくても良いという結論にタカサカの思考は辿りつきました。音のない世界を体験するというのも重要なような気がしました。
「デフ文化」という考えかたもショックでした。乗富秀人さんに出会うまで「聞こえることを日常とする存在」と「聞こえないことを日常とする存在」の差異を考えることなどありませんでした。テレビバラエティーの番組で、字幕で笑わせる弊害が指摘されていましたが、乗富秀人さんたちには便利なようでした。映画を見るにしても、日本映画には字幕がないので外国映画を選ぶのだそうです。
「耳が聞こえる人」と「耳が聞こえない人」の感覚の違い。違いのあることから生まれる文化的差異。双方が滞りなく生活できるトコロ。「デフ文化」への認識が少し深くなった気がしています。
「デフ文化」に触れ、そして互いに交流できる場としての「デフ文化村」。2005年7月16日に実験の場所は閉店したのでした。
彼らの行動力はきっとまた新しい流れを作っていくに違いないと思えるのでした。